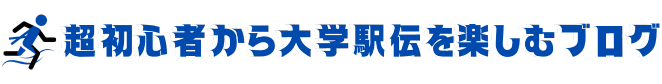大学三大駅伝のひとつとしても知られている全日本大学駅伝ですが、みなさんはどのようにして出場校が決められているのかご存じですか?
なんとなく、予選会とかあるのかな?というイメージはあるかもしれませんね。
私も出場校はどうやって決まるのかとか、代表枠や成績枠という言葉も知らなくて、よく分かっていなかったんですよね。
そこでここでは、全日本大学駅伝に出場できる27チームのうち、日本学連選抜チームと東海学連選抜チームの2チームを除いた25チームについて、どのようにして代表校が決定するのか、その決め方について、詳しくご紹介していきたいと思います。
特に、成績枠というのが少しややこしいかなと思いますので、過去の例を挙げながら分かりやすくお伝えしていきますので、良かったら最後までご覧になってみてくださいね。
全日本大学女子駅伝に関して詳しくはこちら
>>>全日本大学女子駅伝2023(杜の都駅伝)の開催場所は?ライブ配信も
[kanrenc id=”7926″]
全日本大学駅伝の出場校の決め方とは?
それではまず、全日本大学駅伝の出場校27チームのうち、日本学連選抜チームと東海学連選抜チームの2チームを除いた25チームについて、どのようにして代表校が決まるのか?
全日本大学駅伝の代表枠と呼ばれるものについて、解説していきたいと思います。
代表枠25チームの内訳は?
代表枠25チームの中には、「基本枠」「シード枠」「成績枠」の3つがあります。
基本枠・シード枠・成績枠ってなに?
以下で詳しく説明しますね。
基本枠(8枠)・・・全国を8つの地区に分け、それぞれの地区学連で1枠ずつ平等に与えられたもの。
シード枠(8枠)・・・前年度の大会において上位8位以内のチームに与えられた出場枠
成績枠(9枠)・・・前年度の大会において、シード枠以下の9位~17位に該当する大学の所属地区学連に出場枠が分配されるもの。
基本枠の8つの地域ってどこ?
基本枠の8つの地域は、以下になります。
・北海道地区
・東北地区
・関東地区
・北信越地区
・東海地区
・関西地区
・中国四国地区
・九州地区
上記の8つの地区でそれぞれ代表選考会が行われて、出場チームを決定。
なお、各地区学連で行われる選考会の内容(駅伝、ロードレース等)や選考会の開催時期は各地区学連に一任されているので、地区学連によって異なることがあります。
また、前年度大会の9位~17位のチームが所属する地区学連には成績枠がプラスされますので、地区学連によって「代表枠=基本枠+成績枠」が異なります。
成績枠に関しては続く見出しで詳しく解説してきますね。
全日本大学駅伝の代表枠が分かりにくい?51回大会~53回大会を例にして比べてみた!
それでは次に、全日本大学駅伝の代表枠について、もう少し詳しく見ていきたいと思います。
特に、成績枠として出場枠が与えられている前年度大会の9位~17位のチームが、どうやって翌年の地区代表枠に影響しているのか、第51回大会~第53回大会を振り返って、実際の順位と代表枠を比べてみましょう。
第51回大会(2019年)の場合
前年度(2018年)の9位~17位
9位 明治大学 (関東)
10位 神奈川大学 (関東)
11位 日本大学 (関東)
12位 日本体育大学 (関東)
13位 順天堂大学 (関東)
14位 中央学院大学 (関東)
15位 早稲田大学 (関東) ※1
16位 立命館大学 (関西)
17位 京都産業大学 (関西)
18位 皇學館大学 (東海) ※2
関東・・・7枠-1枠=6枠(※1
東海・・・1枠(※2
関西・・・2枠
※補足※
ひとつの地区学連から出場できるのは最大15チームまでと決まっています。
第51回大会の結果を見てみると、シード枠となる上位8チームすべてが関東地区のチームでした。
それに加えて、9位~17位までの7チームも関東地区だったために、基本枠1+シード枠8+成績枠7の合計16となり、出場最大15チームより1チームオーバーしてしまっています(※1)
この場合、関東地区が成績枠を1つ超過した分を18位のチームが所属する地区学連へ分配することとなっていますので、18位の皇學館大学(東海)(※2)が成績枠を獲得し、東海地区に成績枠1が分配されました。
基本的には9位~17位のチームの地区学連に成績枠が分配されますが、出場最大枠を超えた場合には成績枠の分配の調整が行われています。
それでは改めて第51回大会の代表枠をおさらいしてみましょう。
●第51回大会(2019年)の代表枠(基本枠および成績枠)
・北海道地区 (代表枠1) 基本枠1
・東北地区 (代表枠1) 基本枠1
・関東地区 (代表枠7) 基本枠1+成績枠6
・北信越地区 (代表枠1) 基本枠1
・東海地区 (代表枠2) 基本枠1+成績枠1
・関西地区 (代表枠3) 基本枠1+成績枠2
・中国四国地区 (代表枠1) 基本枠1
・九州地区 (代表枠1) 基本枠1
第52回大会(2020年)の場合
前年度(2019年)の9位~17位
9位 順天堂大学 (関東)
10位 中央学院大学(関東)
11位 法政大学 (関東)
12位 立命館大学 (関西)
13位 城西大学 (関東)
14位 日本体育大学(関東)
15位 明治大学 (関東)
16位 拓殖大学 (関東)※1
17位 関西学院大学(関西)
18位 京都産業大学(関西)※2
関東・・・7枠-1枠=6枠(※1
関西・・・2枠+1枠=3枠(※2
※補足※
ひとつの地区学連から出場できるのは最大15チームまでと決まっています。
第51回大会の結果を見てみると、シード枠となる上位8チームすべてが関東地区のチームでした。
それに加えて、9位~17位までの7チームも関東地区だったために、基本枠1+シード枠8+成績枠7の合計16となり、出場最大15チームより1チームオーバーしてしまっています(※1)
この場合、関東地区が成績枠を1つ超過した分を18位のチームが所属する地区学連へ分配することとなっていますので、18位の京都産業大学(関西)(※2)が成績枠を獲得し、関西地区に成績枠1が追加で分配され、関西地区の成績枠の合計は3枠となりました。
基本的には9位~17位のチームの地区学連に成績枠が分配されますが、出場最大枠を超えた場合には成績枠の分配の調整が行われています。
それでは改めて第52回大会の代表枠をおさらいしてみましょう。
●第52回大会(2020年)の代表枠(基本枠および成績枠)
・北海道地区 (代表枠1) 基本枠1
・東北地区 (代表枠1) 基本枠1
・関東地区 (代表枠7) 基本枠1+成績枠6
・北信越地区 (代表枠1) 基本枠1
・東海地区 (代表枠1) 基本枠1
・関西地区 (代表枠4) 基本枠1+成績枠3
・中国四国地区(代表枠1) 基本枠1
・九州地区 (代表枠1) 基本枠1
53回大会(2021年)の場合
前年度(2020年)の9位~17位
9位 國學院大學 (関東)
10位 東京国際大学(関東)
11位 中央学院 (関東)
12位 日本体育大学(関東)
13位 山梨学院大学(関東)
14位 日本大学 (関東)
15位 立命館大学 (関西)
16位 城西大学 (関東)※1
17位 皇學館大学 (東海)
18位関西学院大学 (関西)※2
関東・・・7枠-1枠=6枠(※1
東海・・・1枠
関西・・・1枠+1枠=2枠(※2
※補足※
ひとつの地区学連から出場できるのは最大15チームまでと決まっています。
第51回大会の結果を見てみると、シード枠となる上位8チームすべてが関東地区のチームでした。
それに加えて、9位~17位までの7チームも関東地区だったために、基本枠1+シード枠8+成績枠7の合計16となり、出場最大15チームより1チームオーバーしてしまっています(※1)
この場合、関東地区が成績枠を1つ超過した分を18位のチームが所属する地区学連へ分配することとなっていますので、18位の関西学院大学(関西)(※2)が成績枠を獲得し、関西地区に成績枠1が追加で分配され、関西地区の成績枠の合計は2枠となりました。
基本的には9位~17位のチームの地区学連に成績枠が分配されますが、出場最大枠を超えた場合には成績枠の分配の調整が行われています。
それでは改めて第53回大会の代表枠をおさらいしてみましょう。
●第53回大会(2021年)の代表枠(基本枠および成績枠)
・北海道地区 (代表枠1) 基本枠1
・東北地区 (代表枠1) 基本枠1
・関東地区 (代表枠7) 基本枠1+成績枠6
・北信越地区 (代表枠1) 基本枠1
・東海地区 (代表枠2) 基本枠1+成績枠1
・関西地区 (代表枠3) 基本枠1+成績枠2
・中国四国地区(代表枠1) 基本枠1
・九州地区 (代表枠1) 基本枠1
参考
全日本大学駅伝の出場校の決定方法を解説 順位によって変動する地区出場枠数4years
さて、ここまで代表枠の具体例をご紹介してきましたが、現在のような代表枠が採用されるようになったのは、第51回大会からなんです。
では、第50回大会まではどのような代表枠が採用されていたのでしょうか?
気になる方は、次の見出しもご覧になってみてくださいね。
代表枠数は第51回大会より前と以降で違う?
それでは最後に、第51回大会を機に変わった全日本大学駅伝の代表枠について、それまではどのような代表枠で大会が行われていたのか、簡単にご紹介していきますね。
第51回大会以降
・全国8地区に基本枠を1枠ずつ配分する。
・前年度大会で8位以内の大学にシード権を与える。(シード枠)
・前年度大会で9位~17位のチームの所属する地区学連の数を出場枠として配分する。(成績枠)
・また、第51回大会よりシード権が前年度大会6位から8位以内に変更となったため、成績枠も11枠から9枠に変更されました。
・代表枠は各地区学連につき最大15チーム。(15チームを超える場合は18位のチームが所属する地区学連へ成績枠を分配する)
●具体例:第51回大会(2019年)の代表枠(基本枠および成績枠)
・北海道地区 (代表枠1) 基本枠1
・東北地区 (代表枠1) 基本枠1
・関東地区 (代表枠7) 基本枠1+成績枠6
・北信越地区 (代表枠1) 基本枠1
・東海地区 (代表枠2) 基本枠1+成績枠1
・関西地区 (代表枠3) 基本枠1+成績枠2
・中国四国地区(代表枠1) 基本枠1
・九州地区 (代表枠1) 基本枠1
第45回~第50回大会まで
・全国8地区に基本枠を1枠ずつ配分する。
・前年度大会で6位以内の大学にシード権を与える。(シード枠)
・前年度大会7位~17位の大学の所属地区学連に成績枠計11枠を配分する。(成績枠)
・同一地区から出場できる大学の数はシード校を含め最大15校とする。
●具体例:50回大会(2018年)の代表枠(基本枠および成績枠)
・北海道地区 (代表枠1) 基本枠1
・東北地区 (代表枠1) 基本枠1
・関東地区 (代表枠9) 基本枠1+成績枠8
・北信越地区 (代表枠1) 基本枠1
・東海地区 (代表枠2) 基本枠1+成績枠1
・関西地区 (代表枠3) 基本枠1+成績枠2
・中国四国地区(代表枠1) 基本枠1
・九州地区 (代表枠1) 基本枠1
22回~44回大会まで
・2枠を超える複数枠地区代表の中で最下位校が出た地区は、次の大会において出場枠を基本定数から1枠減らす制度を採用。
・削減された枠は他の地区(基本的は前年に枠を削減された地区)に割り当てられる。
参考
(全日本大学駅伝対校選手権大会)代表枠数の変遷Wikipedia
全日本大学駅伝の出場校の決め方まとめ
全日本大学駅伝の出場校の決め方について解説してきました。
成績枠というのが前年度大会の順位に応じて分配される地区学連が変わってくるので、毎年同じというわけではないというのが、少し分かりにくいところではありますよね。
前回は成績枠が2枠あったのに、今回は1枠しかないのはなんで?って思ったときは、前年度大会で9位~17位に入っているかいないか、チェックしてみると良いかもしれません。
今まで全日本大学駅伝の代表枠ってあまりよく分からなかった、という方の参考になれば嬉しいです。
全日本大学駅伝についてもっと知りたい方はこちら