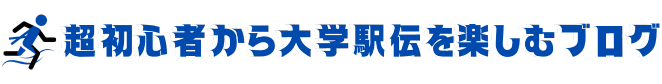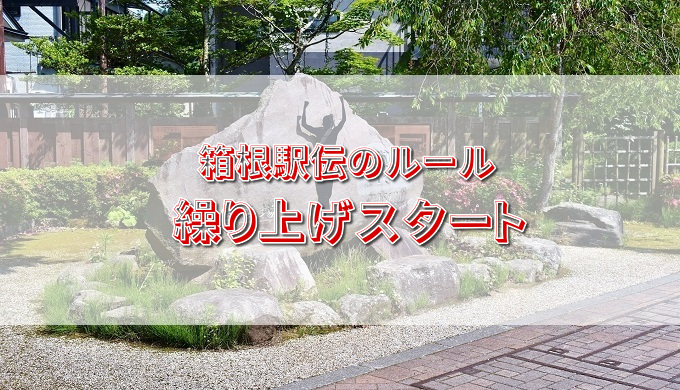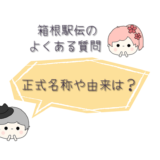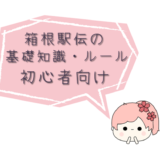箱根駅伝には『繰り上げスタート』というルールがあります。
このルールがあるゆえに、毎年たすきを次の選手に渡せなかった選手たちの姿を観ることになり、切ない気持ちにもなるのですよね。
次の選手にたすきを繋げるために、どれほど苦しくても懸命に走ってきたのに・・・
それなのに、たすきを繋げることができなかった選手の思い。
仲間のたすきを受け取ることができずにスタートしなければならなかった選手のことを思うと、なぜこのような厳しいルールがあるのだろうと感じます。
ただ、繰り上げスタートのルールは、箱根駅伝に関わらず、他のマラソンや駅伝にも採用されているルールでもあるんですよね。
ということで『繰り上げスタート』について、なぜそのようなルールがあるのか?
また繰り上げスタートをした場合にたすきはどうなるか詳しくお伝えしていきます。
超初心者にはこちらがおすすめ
>>>超初心者でもわかる「繰り上げスタート」
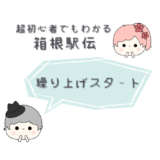 【超初心者】箱根駅伝の繰り上げスタートとは?
【超初心者】箱根駅伝の繰り上げスタートとは?
箱根駅伝の繰り上げスタートの意味やルールとは?
箱根駅伝の繰り上げスタートというのは、どのようなルールなのでしょうか?
箱根駅伝の繰り上げスタート(ルールでは繰り上げ出発)というのは、先頭走者から一定時間離された場合に、前の走者が中継所に到着しなくても次の走者をスタートさせるというルールのこと。
具体的な時間差については、以下のとおり。
1. 往路の鶴見中継所・戸塚中継所・・・10分遅れたチーム
2. 往路の平塚中継所・小田原中継所・・・15分遅れたチーム
3. 復路のすべての中継所・・・20分遅れたチーム
以上の3パターンの場合において、それぞれ該当するチームに適用されます。
第 100回東京箱根間往復大学駅伝競走 競技実施要項
[2] 交通流動の円滑化及び事故防止対策2. 繰り上げ出発 1) 中継所における繰り上げ出発は次の通りとする。
往路鶴見・戸塚中継所で先頭走者通過から 10 分を超えて遅れたチームは、車両の混雑が予想されるため、各中継所審判員主任の裁定により前の走者が到着しなくても次の走者を出発させる。
往路平塚・小田原中継所は 15 分とし、復路すべての中継所は 20 分とする。同時出発が複数校ある場合の並び順は、進行方向左側から前中継所の通過順とする。
2) 復路のスタートは、往路において 1 位チームのフィニッシュから 10 分以内に
フィニッシュしたチームは時差出発を行い、その他のチームは往路 1 位のチームがスタートした 10 分後に同時出発を行う。
分かりやすく言い換えてみるとこういうことですね。
1. 往路の鶴見中継所と戸塚中継所
先頭(1位)の走者から10分経過した段階で、前走者が到着するのを待たずに(前走者からたすきを受け取ることなく)中継所にスタンバイしていた次の選手(10分以上遅れたチームの選手すべて)がスタートする。
2. 往路の平塚中継所と小田原中継所
先頭(1位)の走者から15分経過した段階で、前走者が到着するのを待たずに(前走者からたすきを受け取ることなく)中継所にスタンバイしていた次の選手(15分以上遅れたチームの選手すべて)がスタートする。
3. 復路のすべての中継所
先頭(1位)の走者から20分経過した段階で、前走者が到着するのを待たずに(前走者からたすきを受け取ることなく)中継所にスタンバイしていた次の選手(20分以上遅れたチームの選手すべて)がスタートする。
※ 復路6区のスタート時に行われる復路一斉スタート(繰り上げ一斉スタート)と混同されることがあるのですが、別のルールになります。
復路一斉スタート(繰り上げ一斉スタート)についてはこちら
>>>箱根駅伝の復路一斉スタートの意味とは?
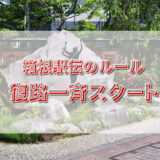 箱根駅伝の復路一斉スタートの意味とは?最多記録やたすきについても
箱根駅伝の復路一斉スタートの意味とは?最多記録やたすきについても
箱根駅伝の繰り上げスタートのルールはなぜあるの?
繰り上げスタートというのがどのようなルールかは、理解していただけたと思います。
でもなぜ、繰り上げスタートというルールがあるのでしょうか?
それは、ルールにも書かれているのですけれど、車両混雑が予想されるためです。
箱根駅伝をはじめ、他のマラソンや駅伝も競技ルートは一般道を利用していますよね。
そのため、競技中は交通規制が行われていて、年間を通じて交通量が少ない日程と時間帯に箱根駅伝を開催しているものの、少なからず渋滞が起きているとも言われています。
つまり、交通規制をすみやかに解除するという目的で、繰り上げスタートというルールがあるんですよ。
とはいえ、中継所まであと少しというところでの繰り上げスタートは、選手たちはもちろんのこと見ている方も辛いですよね。
でもだからこそ、辛くても、どんなにきつくてもたすきを繋げようと選手たちは懸命に走れるのかもしれません。
箱根駅伝が害悪と言われる理由に関してはこちら
>>>箱根駅伝が害悪大会と言われる理由とは?
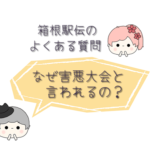 箱根駅伝が害悪大会と言われる理由とは?弊害で燃え尽きる選手もいるの?
箱根駅伝が害悪大会と言われる理由とは?弊害で燃え尽きる選手もいるの?
繰り上げスタートになった場合たすきはどうなるの?
箱根駅伝に出場する選手は、大学のカラーのたすきを掛けています。
たすきを繋ぐということにも大きな意味がある箱根駅伝ですが、前走者を待たずにスタートする繰り上げスタートが行われた場合、このたすきはどうなってしまうのでしょうか。
その点もルールで決められています。
第 100回東京箱根間往復大学駅伝競走 競技実施要項
[1] 概 要 1. 服 装 アスリートビブス た す き5) 繰り上げ出発のチームは、主催者が用意する黄色と白色のストライプのたすきを使用する。
ただし、5 区、10 区は各チーム独自のたすきを使用する。
なお、途中棄権したチームも、次区間からは主催者が用意する黄色と白色のストライプのたすきを使用し、10 区のみ各チーム独自のたすきを使用する。
繰り上げスタートとなったチームの選手は、大会本部が用意した「黄色と白のストライプのたすき」を掛けてスタートします。
ルールと分かっていても、大学のたすきではないたすきを掛けて走っているのを観ると、やっぱり何か物足りないと言うか、寂しい気持ちになってしまいますね。
ただし例外の区間があって、往路のゴールである5区と復路のゴールである10区では、大学が用意したたすきを掛けることができます。
その際は、5区または10区の走者が既に大学のたすきをかけている状態で待機していて、前走者から白たすきを受け取った後にスタートしますが、白たすきはスタッフに渡すなどして手放すそう。
ゴール地点は大学のたすきで、という運営側の配慮なのではないかとも言われています。
1本のたすきを繋ぐことはできないけれど、大学のたすきでゴールができるというのは選手にとっても、応援する人たちにとってもありがたい配慮だと感じますね。
箱根駅伝のたすきのルールについて詳しくはこちら
>>>箱根駅伝のたすきのルールとは?
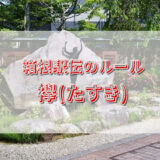 箱根駅伝の襷(たすき)のルールとは?繰上げスタート時は色が違う?
箱根駅伝の襷(たすき)のルールとは?繰上げスタート時は色が違う?
繰り上げスタートになった場合の記録はどうなるの?
繰り上げスタートになった場合の記録はどうなるのでしょうか?
繰り上げスタートになって、大学のたすきを繋げることはできなくなったとしても、失格というわけではありません。
前の区間の選手が中継所まで走りきれば、レースそのものはつながっていて、タイム記録は通算されますので、遅れた時間を測定し合計タイムに加えます。
タイム記録は、それぞれ公式記録として残るので安心してくださいね。
チームの総合順位は、見た目のタイムに繰り上げ分の時間差を加算して算出されます。
繰り上げ出発が行われた場合(特に復路の場合)には、走っている見かけ上の順位と、実際の順位(合計タイムでの順位)が異なるので分かりにくいかもしれませんね。
箱根駅伝の最終的な順位はあくまでも、ゴールに到達した見た目の順位ではなく、合計タイムで順位が決まるということを覚えておいてください。
箱根駅伝繰り上げスタートからの逆転優勝はあるの?
それでは最後に、「繰り上げスタートからの逆転優勝」について触れてみたいと思います。
駅伝の選手は1kmを3分目安で走っているので、これを時速に直すと時速20km前後になると言われています。
50mを9秒で走り続ける、と言った方が分かりやすいかもしれませんね。
50mをダッシュするのではなく、それを1区間キープしながら20km近く走り続けているのですから、相当速いということが想像できるのではないでしょうか。
もちろん、一定の速さで走ることは難しいので、途中でペースダウンすることも考えられますよね。
そうした中で、過去にどのくらいの時間差を逆転したことがあるのか調べてみたところ、1986年には6分32秒差を、その翌年には3分55秒差を逆転して順天堂大学が連覇を果たした事がありました。
しかし、5分を超える時間差の逆転はごく稀なことで、おおよそ3分の差であれば逆転の可能性はあると考えられると言われています。
3分といえば一つの目安である1kmのラップタイムですから、繰り上げスタートの10分遅れの場合は距離にして3kmあまり、20分遅れの場合は6kmあまり離れていることになります。
2016年に開催された92回大会の結果を見てみると、往路1位の青山学院大学と2位の東洋大学の差は3分04秒差でした。
復路でもその差は縮まらず、7区から10区までこの2校の順位の変動はないまま最終的に青山学院大学が優勝、復路は4分07秒差となっていました。
また、復路と往路の記録を合わせて決まる総合順位では、6区でのみ復路一斉スタートした3校だけが健闘して10位以内に入っただけで、その他の区間で複数の繰り上げスタートをしたチームのほとんどは11位以下という成績。
逆に言うと、総合順位で10位以内に入るチームの大半は繰り上げスタートを行っていないということになります。
過去5年間の記録を見ても同じで、繰り上げスタートを行ったか、行っていないかでシード権が与えられる10位以内に入れるか否かが決定するようですね。
以上のことを踏まえると、繰り上げスタートからの逆転優勝は、ほぼ不可能だと考えられます。
しかし、棄権とは違い記録や順位は公式に残りますから、1分でも1秒でもタイムを縮めて、翌年に繋がるような走りを見せて欲しいですね。
箱根駅伝の棄権のルールに関して詳しくはこちら
>>>箱根駅伝での棄権に関するルールとは?
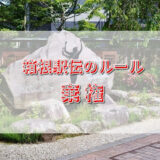 箱根駅伝での棄権に関するルールとは?記録の扱いとその後についても
箱根駅伝での棄権に関するルールとは?記録の扱いとその後についても
箱根駅伝の繰り上げスタートまとめ
繰り上げスタートというルールがあるのは知っていましたが、これほどまでに順位に影響するとは思いませんでした。
総合順位で10位以内に入るチームは、まさに総合力が強く、たすきを繋ぐ力を持ったチームと言えるのかもしれませんね。
たすきの色を見ればそのチームがどういう状況なのかも分かるようになりました。
繰り上げスタートがあるので、たすきを繋げるかどうかの時にはハラハラしたり、繰り上げスタートを回避できた時には私までガッツポーズしたり、残念ながらたすきを繋げなかった場合には胸が苦しくなったりと観戦しているだけなのについつい感情移入して、最後まで目が離せないというのもあるのですよね。
でも、出来るだけ繰り上げスタートする大学チームがないといいなと毎年願いながら見てしまいます。
箱根駅伝のルールや出場校について詳しく知りたい方はこちら