箱根駅伝のテレビ中継を見ていると、『シード権』とか『シード権争い』、または『シード校』という言葉を多く耳にします。
箱根駅伝を見始めてまだ日が浅いという方にとっては、耳慣れない言葉かもしれませんね。
実は、箱根駅伝には” たすきを途切れることなく最後まで繋ぐ ” という目的もありますが、” シード権を獲得する ”というのも目的の一つであり、非常に重要なんですよ。
ということで、シード権とは何か?
また、なぜ獲得することがそれほど重要なのか?
という点について、分かりやすく説明してしていきます。
更に、2025年1月2日と3日に開催予定の第101回箱根駅伝のシード権を獲得している大学(シード校)についてもお伝えしますね。
超初心者にはこちらがおすすめ
>>>超初心者でもわかる「箱根駅伝のシード権」
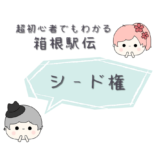 【超初心者】箱根駅伝のシード権とは?条件や決め方は?
【超初心者】箱根駅伝のシード権とは?条件や決め方は?
箱根駅伝のシード権のルールとは?何位まで獲得できる?
まず、箱根駅伝のシード権のルールについて説明しましょう。
箱根駅伝の正式名称は、『東京箱根間往復大学駅伝競争』。
主催は関東学生陸上競技連盟。
出場校は全て関東の大学で、関東学連加盟校以外の大学は出場できません。
毎年、1月2日と3日の2日間に渡って往路と復路を走り、その総合成績で順位が決まります。
そして、その年の箱根駅伝で総合成績上位10校(1位~10位の大学)には、予選会なしで翌年の箱根駅伝に出場できる権利が与えられます。
それが『シード権』。
第100回東京箱根間往復大学駅伝競走
第100回東京箱根間往復大学駅伝競走 開催要項
開催要項
12. シ ー ド 権
当駅伝競走に関する内規第4 章「参加校数、シード校数、予選会」第13 条に基づき、本大会で
10位までに入った大学は、第101 回東京箱根間往復大学駅伝競走のシード権を取得する。
具体例をあげて説明すると、2024年の箱根駅伝でシード権を獲得した大学(1位~10位の大学)は、2025年の箱根駅伝の出場が自動的に決まるということ。
シード権を獲得した上位10校の大学は、『シード校』と呼ばれます。
箱根駅伝は、記録が残らないオープン参加である関東学生連合チームを除いた、20校で競われます。
20校のうち10校が前回大会の総合成績上位10校、つまりシード権がある大学ということになるんですね。
※ 第100回箱根駅伝は記念大会で、出場枠が23校に増枠。
※ 関東学生連合チームの参加なし。
では、残りの10校はどのようにして選ばれていると思いますか?
毎年10月、箱根駅伝の残り10校の出場枠をかけた予選会が行われているんです。
予選会にエントリーする大学は40校前後、2022年に行われた箱根駅伝2023の予選会では43校が出場しました。
この予選会の上位10校が、箱根駅伝に出場できるのです。
つまり、40校前後の大学が参加する予選会で、10位以内に入らないと予選会を通過できないということ。
40校中の10校という数字だけを取って見ても、とても狭き門であることが想像できますよね。
シード権を獲得できれば、競争率の高い予選会の出場が免除されます。
予選会に出場しなくても箱根駅伝に出場できるというのは、それだけでも大きなメリットがあると言えますよね。
そう考えると、予選会なしで翌年の箱根駅伝に確実に出場できるシード権が、よりいっそう魅力的に見えてきませんか?
続く見出しでは、箱根駅伝でシード権を獲得することが重要な理由について、さらに詳しくお伝えしていきますね。
※ 第100回箱根駅伝は記念大会で、予選会通過枠が13校に変更
2023年10月14日に開催された箱根駅伝2024予選会。
第100回目の記念大会ということで参加出来る大学の範囲が全国に広げられ、普段は関東の大学にしか開かれていない機会が地方の大学にも開かれました。
残念ながら地方から11校の大学が参加するも、地方と関東の実力差はまだまだ大きく予選会を突破して本戦に出場することは叶いませんでした。
詳しくは以下の記事を参照
箱根駅伝のシード権を獲得することが重要である理由とは?
前の見出しから、予選会なしで翌年の箱根駅伝に確実に出場できる権利を『シード権』と言うことは、もう分かりましたよね。
そして、シード権がない大学は、予選会を通過しなければならないということもお分かりいただけたと思います。
この予選会も近年は全体の実力が上がってきていて、箱根駅伝本番さながらに準備をして迎えないと、上位は狙えないとも言われてるんですよね。
10月の予選会を通過したとしても箱根駅伝までは2ヶ月余り、選手の疲労回復と再び箱根駅伝に向けて立て直さなければならないという課題が出てきます。
また、予選会に向けては8月頃から調整をしなければならないとも言われていて、これは選手や駅伝メンバーを選出するチームにとっても、大きな負担となっているようなんですね。
学生三大駅伝と呼ばれる10月の『出雲駅伝』、11月の『全日本大学駅伝』、1月の『箱根駅伝』、この中の『全日本大学駅伝の関東予選』は6月に行われます。
こうした駅伝大会の年間スケジュールの中、選手が何度も万全の状態で、大会にピークを持っていくのは容易なことではないでしょう。
予選会に出場する必要がなければ、本戦に集中して尽力出来るので選手やチームにかかる負担も軽減されますよね。
また全日本大学駅伝など他の駅伝に向けても調整がしやすくなりますから、こういった理由からもシード権は重要になってくると考えられるんですよ。
さらに、他にもシード権を獲得する大きなメリットが大学側にもあります。
少し見方を変えてみると、箱根駅伝は関東の大学しか出場しない、いわば関東ローカルの駅伝にも関わらず全国放送されていますよね。
シード圏内を走っている10位以内の大学は、テレビ中継でも多く映し出されます。
そうなれば大学の名前は日本各地に知れ渡ると当時に、駅伝が強いというブランドもついて、その大学に入る新入生の増加も期待できますし、実際に関東の大学とはいえ出身高校が東北や関西、九州の選手が多いこともそのことを証明していますよね。
シード圏内を走っていてテレビにも良く映ることで大学の宣伝効果にも繋がり、さらにシード権を獲得すれば予選会が免除になり、大きな大会に向けてチームとしての目標が明確になるというのは、メリットとしてはかなり大きいといえるのでは?
このようにシード権を獲得することは、箱根駅伝だけの特権ではなく、大学そのものや駅伝チームを作り上げる上でとても重要なのですよ。
箱根駅伝の出場条件についてはこちら
>>>箱根駅伝の出場条件や資格とは?関東以外資格がない?
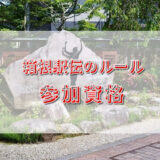 箱根駅伝の出場条件や資格とは?関東圏以外の大学は参加資格がない?
箱根駅伝の出場条件や資格とは?関東圏以外の大学は参加資格がない?
第101回箱根駅伝(2025年)のシード校一覧
それでは次に、第100回箱根駅伝(2024年)の総合順位1位~10位つまり、第101回箱根駅伝(2025年)のシード権を獲得したチームについても見ていきましょう。
| 箱根駅伝2024の総合順位(箱根駅伝2025のシード校) | ||
| 順 位 | 学 校 名 | 記 録 |
| 1位 | 青山学院大学 | 10時間41分25秒 |
| 2位 | 駒澤大学 | 10時間48分00秒 |
| 3位 | 城西大学 | 10時間52分26秒 |
| 4位 | 東洋大学 | 10時間52分47秒 |
| 5位 | 國學院大學 | 10時間55分27秒 |
| 6位 | 法政大学 | 10時間56分35秒 |
| 7位 | 早稲田大学 | 10時間56分40秒 |
| 8位 | 創価大学 | 10時間57分21秒 |
| 9位 | 帝京大学 | 10時間59分22秒 |
| 10位 | 大東文化大学 | 11時間00分42秒 |
以上の10校が2025年1月2、3日に開催される第101回箱根駅伝に出場が確定しています。
第100回箱根駅伝予選会の結果についてはこちら
>>>箱根駅伝2024予選会の結果と順位は?出場校一覧も
箱根駅伝のシード権まとめ
箱根駅伝のシード権について、翌年の箱根駅伝に予選会なしで出場できる権利であること、また箱根駅伝のシード権を獲得することが重要である理由についてもお伝えしてきました。
予選会を免除されるということは、選手にとって体力・時間・精神的な負担の軽減、主要な駅伝の大会に集中して尽力出来るという大きなメリットがあります。
また、大学には全国放送のテレビで宣伝されるという大きなメリットがあることも分かりました。
これまでの箱根駅伝の記録を見てみるとシード権を獲得している大学の半数以上は、その前の年からシード権を持ち続けています。
そう考えると優勝ももちろん大切ですが、それ以前にシード権を獲得することも、翌年以降のレース展開を有利に運ぶための大事な要素なのだと強く感じました。
それだけにシード権を逃すということは、大きなダメージになるのでしょうね。
シード権がある大学は続けてシード権を獲得できるよう、またシード権がない大学は次こそシード権を獲得できるよう、頑張って欲しいと思います。
箱根駅伝のルールや出場校について詳しく知りたい方はこちら
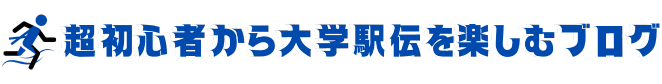
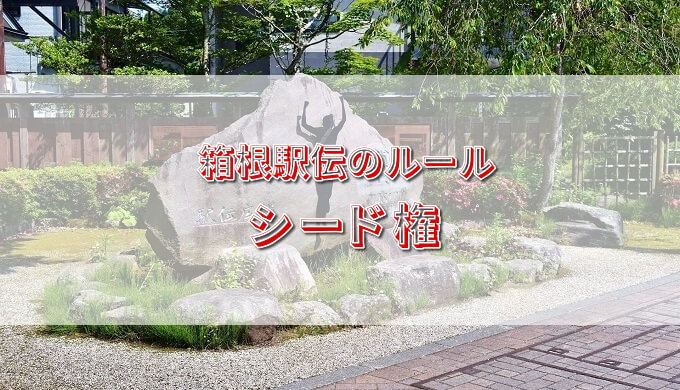
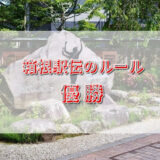

「風が強く吹いている」を見ていて、シード権を獲得しても翌年メンバーが10人未満になった場合は?
青年実業家さん、コメント頂きありがとうございます。
「シード権を獲得しても翌年メンバーが10人未満になった場合は?」という質問にお返事させていただきますね。
実は、箱根駅伝は毎年『東京箱根間往復大学駅伝競走 開催要項』、『同競技 実施要項』ならびに『同駅伝競走に関する内規』に基づいて実施されています。
※以下は、第 96 回東京箱根間往復大学駅伝競走の競技実施要項・内規から引用した内容です。
” 第 96 回東京箱根間往復大学駅伝競走
競技実施要項
[1] 概 要
2. 走行方法
1) 各チームとも、各区間 1 名の競技者で競走し、伴走は一切認めない。
2) 各競技者とも出場は 1 区間に限る。 ”
https://api.hakone-ekiden.jp/storage/top_setting/tournament/48.pdf
出典:東京箱根間往復大学駅伝競走公式HP 第 96 回東京箱根間往復大学駅伝競走 競技実施要項
”
東 京 箱 根 間 往 復 大 学 駅 伝 競 走 に 関 す る 内 規
第5章 競技細則
第15条(概要、走行方法)
①各校各区間とも1名の競技者で走行し、伴走は一切認めない。
②各競技者とも走行は1区間に限る。 ”
https://web.archive.org/web/20141015153600/http://www.kgrr.org/event/2006/kgrr/83hakone/83naiki-new.pdf
出典:Wayback Machine 東 京 箱 根 間 往 復 大 学 駅 伝 競 走 に 関 す る 内 規PDF
各区間1名の競技者で、しかも各競技者の出場は1区間のみとあり、言い換えると、10区間を10人の競技者で走ることがルールで定められているんですね。
上記から、実際に競技に参加するのが10人未満では参加資格がないと考えられます。
現実的に考えて、シード権を獲得しても翌年の箱根駅伝(当日含む)までにどのような問題やトラブルが起こるか分からないので、もしもの時を考えて補欠メンバーを予めチームに加えておくのはリスクヘッジの上でも重要なことと言えます。
そういう事態も当然想定して、エントリーできる選手に関して『正競技者10 名 補欠競技者6 名以内』と、実際に走る正競技者に加えて補欠競技者も6名以内までエントリー可能になっているのかと。
参加資格に関しては他にも細かな規定がありますので、サイト内で具体的にケースバイケースでお伝えできればと思っています。
シード権争いで同着なら、タイムがはやいほうで、決定するのですか?
あけみさん
コメント頂きありがとうございます。
箱根駅伝の順位は、タイムで決まりますので、タイムの順位が公式の順位になります。
もしも、タイムが同じ場合には、以下のルールに従って順位が決まることになっています。
第98回東京箱根間往復大学駅伝競走 競技実施要項
[1] 概要
5. 同タイムの順位
繰り上げ出発等により、フィニッシュの着順が成績順位を示さない場合の同タイム大学の順位は、区間上位者数の多少によるものとする。
すなわち、まず区間1位の数で比較し、それが同数の場合は区間2位の数と、ひとつずつ順位を下げて数を比較し、多い 大学を上位とする。
ただし、それでもなおすべて同数の同タイム大学がある場合は同順位とし、それが10位以内の場合はすべての大学が次回大会へのシード権を取得する。
箱根駅伝公式サイト 第98回東京箱根間往復大学駅伝競走 競技実施要項
参考になりましたら幸いです。
コメント失礼致します。上位10位に入った大学は無条件でシード権が与えられるのですよね?なのにシード権争いに又出場するのは何故ですか?素人ですみません。
shibahanaさん
コメント頂きありがとうございます!
毎年、次の年の箱根駅伝に無条件に出場できるシード権を獲得するためにシード権が争われています。
2022年第98回箱根駅伝で上位10位に入った大学は・・・2023年第99回箱根駅伝に出場できるシード権を獲得し、実際に出場。
2023年第99回箱根駅伝で上位10位に入った大学は・・・2024年第100回箱根駅伝に出場できるシード権を獲得。
シード権は次の年だけ有効で、永続した権利ではないので、毎年次の年のシード権を獲得するために10位以内に入れるよう熾烈な競争があるのです。
説明が下手でよくわからないようでしたらまた教えて下さい。